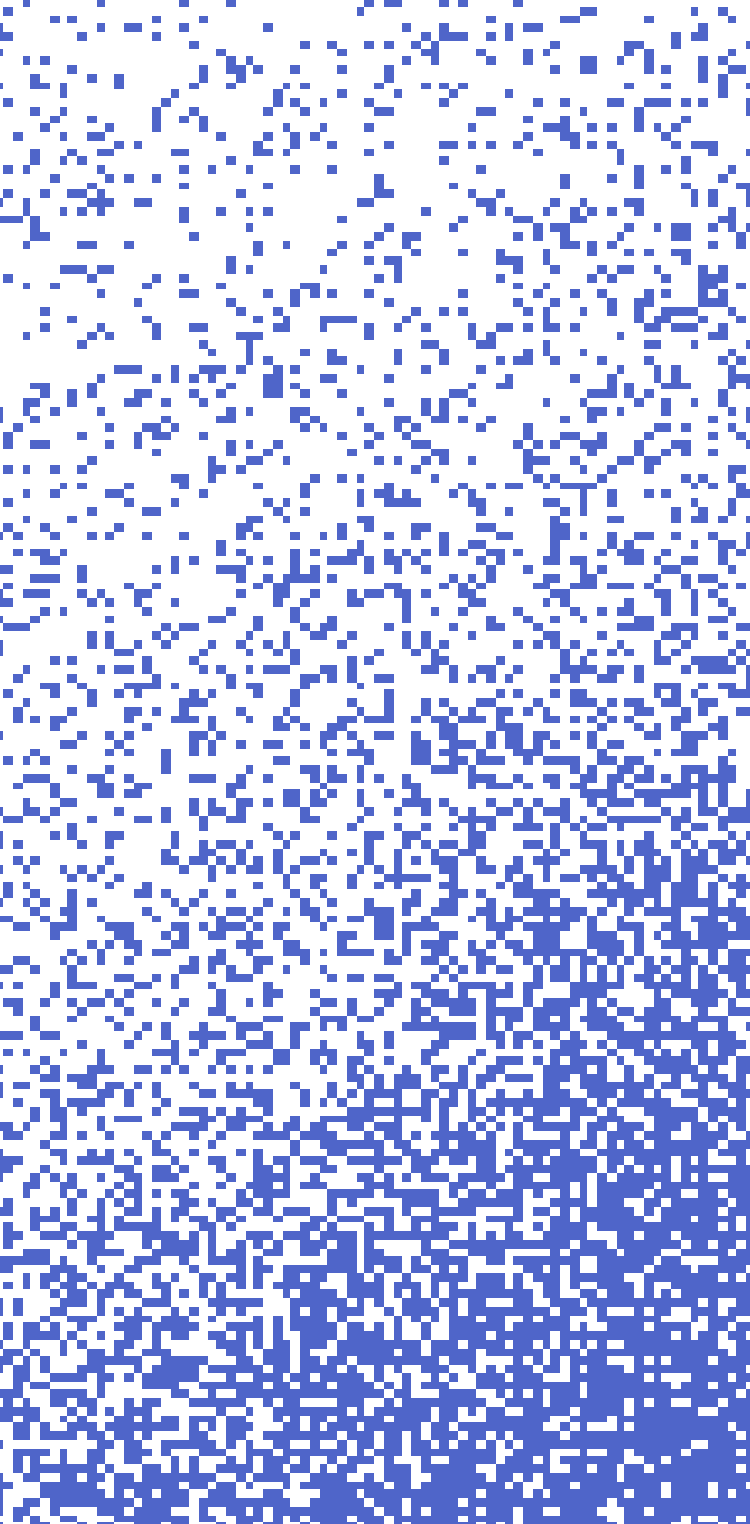さまざまな分野の第一線で活躍する起業家を招き、”起業”のリアルを理解できるイベントCROSSING DAY。大いに盛り上がり、大好評だった第1回が記憶に新しいですが、去る9月19日、第2回「CROSSING DAY 2025 SUMMER」が開催されました。
今回も、個性的な起業家によるリアルな体験やアドバイスが満載!第2回は、「自分らしい起業の育て方」をテーマに熱いトークが繰り広げられました。「CROSSING DAY 2025 SUMMER」の様子をレポートします。
目次
第2回CROSSING DAYを飾る個性的な2人のパネリストが登壇!

左:平藤 篤氏 右:山根 弘成氏
経営学部教授伊藤智久先生から、今回のテーマとMeisei Crossing Baseの概要について簡単に紹介いただき、イベントがスタート。Meisei Crossing Baseとは、「クロッシングから生まれる私たちの未来」をコンセプトにしているプロジェクトです。
明星大学は9学部1学環が1つのキャンパスにあるめずらしい大学。しかし、学部の垣根を超えた交流や情報交換がなかなかなされていない現状があります。さまざまな知識や専門性が交わる=”クロッシングする”ことで、何か新しいものが生み出されるのではないだろうか。そしてそれをビジネスとして、さまざまな地域課題、社会課題を解決するものを生み出していきたいという思いで起ち上げたプロジェクトです。
第2回は、デザイン学部教授 萩原修先生がモデレーターとして進行を務めました。萩原先生は12年前に明星大学でデザイン学部が始まった頃から教鞭を取っており、Meisei Crossing Baseではデザイン面からサポートしています。
今回は、デザイン学部、経営学部それぞれで非常勤講師を務めている2名の起業家に登壇いただきました。
- 平藤 篤 氏(株式会社マルチプル 代表 プロジェクトマネージャー)
- 山根 弘成 氏(ディップ株式会社 BizOps本部エキスパート)
萩原先生は、現代ではインターネットの存在により、小中学生も含め、年齢問わず起業のチャンスが広がっているといいます。今回のパネリストは、インターネットを軸に起業した、あるいは起業支援をしてきた方々。インターネットやウェブを起業にどう活用していくか、それらをビジネスに活かし加速させているお2人です。全く違うキャリアを持ちながらも、共通する部分も。どのようなキャリアを歩んでこられたのかをお2人に語っていただきました。
平藤 篤 氏の起業のきっかけとは?そのキャリアに迫る

プロジェクトの進行管理を生業とする株式会社マルチプル代表 平藤 篤氏(以下平藤氏)は、プロジェクトマネージャー、ウェブディレクターなどの顔を持つ起業家。学生の頃にウェブの制作会社の起業メンバーとしてキャリアをスタートさせたそうです。ご自身のキャリアについて詳しく語っていただきました。
平藤氏:
「デジタルのクリエイティブを中心にプロジェクトを伴走する、いわゆる進行管理をしています。進行管理をする上で、合意形成なども必要なので、ワークショップデザイナーという肩書も持っています。
東京経済大学在学中に会社を立ち上げたので、業界でのキャリアは20年以上ですね。デザインの専門分野の学科ではなかったのですが、ウェブ制作をしている先輩に出会い、遊び感覚で取り組んでいるうちに、いつの間にか仕事をしていたような感じです。」
平藤氏は、近年よく見られるようなスタートアップのような形ではなく、部活動の延長のような感覚で没頭していたことがいつの間にか仕事になり、会社に成長していたような感覚だといいます。なぜ「会社」という形を選んだのでしょうか。
平藤氏:
「最初に起業した会社の仕事は本当に楽しくて、先輩と一緒にずっとホームページ制作をしていたんです。それが自然と仕事になっていって、最初は3人でスタートしました。僕はその会社に12年間いたんですけど、最終的に20~25人くらいの規模にまでに社員が増えました。
当時は、個人事業主で少人数よりも、みんなで組織として活動した方が社会的なインパクトが大きいだろうという考えから法人化しました。なので、楽しいことを続けるための手段として法人化した感覚でした。」
楽しくても、最初からすべてが順調だったわけではなかったのでしょうか。起業のリアルについて、平藤氏はこう語ります。
平藤氏:
「会社が大きくなっていき、知名度もついてきたものの、制作会社経営の難しさを感じていました。当時は代理店から仕事の相談をいただき、約2週間後に企画とデザイン提案するのが一般的だったのですが、こちらからの一方的な提案で本質的にクライアント企業のことを理解できているか?と違和感を覚えはじめたんです。
そこからはクライアント企業から直接仕事をもらうような戦略として、僕らしかできないアウトプットをつくり続けるスタイル(ラボラトリー戦略)に舵を切りました。つまり、社会的な評価を得るための賞を取るようなウェブサイトを戦略的に制作するようにしていきました。その戦略は当たって、徐々に知名度や社会的評価が上がっていき、クライアントから直接の相談が来るようになってきました。さらに、そういったかっこいいウェブサイトをつくりたい!といって才能ある人材がたくさん集まってきたことも嬉しかったです。
その頃から案件も、採用も良い循環になってきていました。それまでは代理店からの仕事で夜中まで作業しているような不夜城な会社だったのが、転換してきた時期です。
一方で、お世話になっていた中小企業さんのプロジェクトなどは予算の関係上お断りせざる終えない状態になり、ふとそんなところに違和感を覚えてはじめたのが独立のきっかけでした。」
平藤氏のキャリアを聞く限り、”気づき”や”違和感”、”楽しさ”など、自分の心のなかに湧き上がる気持ちは、起業においてとても大切なことなのかもしれません。
会社員×起業家 2つの顔を持つ山根 弘成 氏のキャリアに迫る

次に、会社員でありながら個人事業主としての顔も持つ山根 弘成 氏(以下山根氏)に、ご自身のキャリアを語っていただきました。
山根氏:
「バイトルでおなじみのディップ株式会社に勤めており、今年で14年目になります。現在はBizOps本部(BizOps=ビジネスオペレーションの略)に所属し、会社全体の業務効率化とAI推進を担当しています。並行して、AI専門メディア「AINOW」の編集長も務めており、個人事業主としてもAI領域を中心に活動しています。
前半のキャリアでは、ほぼすべての時間を新規事業開発に注いできました。中でも、アニメの聖地を検索できるサービスが流行語大賞を受賞したことは、最も大きな成果のひとつです。
また、音声解析の仕組みを独自に考案して実現したサービス「ANIVO」では、特許を取得しました。これら2つが代表的な実績になります。
かつては年間100名ほどの学生メンタリングも行っていましたが、現在は主にAI活用や業務オーケストレーションの推進に注力しています。これらの活動が、今のキャリアの中心を成しています。」
実に幅広い分野の新規事業を起ち上げることに携わってきた山根氏。会社員でありながら、個人事業主もしている山根氏のキャリアにも、起業のヒントが多くありそうです。
起業・ビジネスに欠かせない視点・ポイント

平藤氏、山根氏のお2人のキャリアを聞いてみると、起業やビジネスに欠かせない要素が多くあったように思います。萩原先生のコメントとともに、トークのなかで見つけた起業・ビジネスのヒントになるような視点やポイントをまとめてみました。
走り続けること
山根氏:
「平藤氏のようなケースは、私のキャリアの中でも多く見てきたパターンだと感じました。
ただ、起業家として走り続けることは本当に難しく、多くの人は途中で会社員に戻ったり、誰かの下で再出発する道を選んだりします。
その中で、変わらず走り続けているのは本当にすごいことだと思います。」
クリエイティブ×ビジネス クオリティの担保と人材

萩原先生:
「平藤さんのお話で大きなポイントが1つあって、仕事をがむしゃらにして、どんどん仕事を取ってきて、会社がだんだん大きくなって、戦略を…という話がありましたね。多分これは”差別化”の話だと思うんですけど、誰でもできる仕事だと買い叩かれて安くなってしまうのはよくある話です。
平藤さんは、”基準となる予算以下ではやらない”ということに違和感を持って独立されました。でも、単価もクオリティも上がり、知名度もついて仕事が増えるということは、事業がうまくいっていることだと思いますが、どうやってクオリティを上げていったのですか?
例えば、価値を作る人材も賞を取ってから集まるのはわかるのですが、最初にクオリティアップをどう目指したのか、そこに苦労はあったのか、そのあたりはどうだったのでしょう?」
平藤氏:
「制作は人材と会社としての目指す方向性次第なので、その2つが揃えばクオリティが上がります。ちょうど僕らがラボラトリー戦略を打ち出した頃に、そういうすばらしい人材が育っていたことが大きな要因だったと考えています。」
萩原先生:
「新たに優秀な人材を採用したのではなく、育ってきた?」
平藤氏:
「そうです。どうしてそういう人材が育ってきたかというと、状況が厳しい時期にも、クリエイティブへの想いを捨てずにがんばっていたからだと思います。クライアントもこだわらない小さな部分にもこだわって制作に向かい合っていました。
例えば、クライアントにとっては「赤でも白でもどっちでもいいよ」というところにも僕らは本質こだわって、提案をしていたんですね。そういった姿勢に人がついてきたし、クライアントの信頼も獲得できたのだと思います。今振り返るとこういうことで会社のカルチャーが醸成されていたのかもしれません。」
萩原先生:
「僕はデザイン学部なのでどうしてもクオリティ重視なんですけど、東京経済大学のような経営を学ぶ環境で、クリエイティブのクオリティにこだわりを持つ人がいたということですか?」

平藤氏:
「そうですね、最初からクリエイティブにクオリティを求める人が代表だったし、彼がデザイナーでした。競争戦略的なところでいうと、当時は競合があまりいないなかで需要は多くあったんです。つまり、ライバルはいないけど、ホームページを作りたい人はたくさんいたんですよね。でも続けていくうちに競合が増えてきて、そうなると価格競争で薄利多売のような感じにもなってくる。そこで、僕らは僕らにしかできないことをやるという戦略にシフトしていったわけです。」
山根氏:
「時代の流れに逆らうような選択をすることも多く、会社にとって私は扱いづらい存在かもしれません。
それでも、自分の信じた方向を貫いてきたことが、結果的に流行語大賞などの成果につながったと感じています。
私にとってのクリエイティブとは、”信じたものを社会に認めさせること”。この姿勢が一貫した信条です。」
萩原先生:
「自分がとにかくこれ!というものを信じて、マーケットがあるからというよりも、自分がやりたいと思うことをやるということなんでしょうか。」
山根氏:
「そうですね。例えばAppleもそうです。市場がまだ求めていなかった時代に、誰もiPhoneを知らなかった頃から「これからはiPhoneが主流になる」と信じ、消費者を教育していきました。
世界最高峰のデザイン集団ともいえるAppleが示したように、想いを伝え、それを理解してもらい、手に取ってもらう——そこにこそクリエイティブの原点があると思います。」
山根氏の得意分野に見る起業に必要なスキル

山根氏:
「自分を構成する要素は何かと考えたとき、3つのスキルに集約されると思います。
これらをひたすら磨いてきました。
①再現性ある仕組み化
自分と同じことを他の人も同じように再現できる仕組みを作れないと、事業は続けられません。だからこそ、再現性のある仕組み化にこだわってきました。
②抽象から具体への翻訳力
デザインのような抽象的なものを言葉で説明するのは、専門家でも難しいものです。
「なぜ丸い形状にしたのか」「なぜ角ばった印象にしたのか」と問われても、説明できる人は少ない。
私は、そうした“感覚の領域”を具体的な言葉に変換するのが得意だと気づきました。
③アドリブ力
仕事も人生も計画通りには進みません。
そういうときに別の分野や発想を持ち込めるかどうか。
新規事業を続ける中で自然に身についた力ですが、今では大きな武器になっています。
これらのスキルは、もともと持っていたものではありません。
誰でも、これから意識すれば身につけられるものです。
だからこそ、起業を目指す人たちにはぜひトライしてほしいですね。
そして今振り返ると、理想的な“クロッシング(交差点)”とは、仕組み化とアドリブの両輪を回すことだと気づきました。
かつては「再現性」にこだわりすぎて、変化に対応できない壁にぶつかった。
そのときに必要だと痛感したのが、アドリブ力でした。」
明星大学らしい起業とは?

今回のテーマである「自分らしい起業の育て方」に関連して、明星大学らしい起業というのが、平藤氏、山根氏から見てどのようなものなのかを聞いてみました。
平藤氏:
「感覚でいうと地域と近い学生が多く、地方から出てきている人は少ない印象。家が自営業という家庭の学生が多いイメージです。私も出身が東村山なので多摩エリアですけど、エリアを盛り上げるハブになるようなイメージですかね。」
萩原先生:
そこから起業につながるというのが、どんなことなのでしょうか。地域とつながっていて、親もサラリーマンではなくて、どう起業に結びつけられるでしょうか。」
平藤氏:
「私は学生で起業したので、就活をしていないからあまりわからないのですが、大規模な合同説明会に参加していない企業のなかにも優良企業はたくさん存在すると感じています。新卒者には接点を持てない、魅力的な企業が多いと感じます。多摩エリアにもそういう企業が多いはずで、今僕がこの歳になって、学生がそういう企業に出会える機会がないというのが残念だなと感じています。」
山根氏:
「明星大学の学生は──あくまで私の印象ですが──心に青い炎を灯した、少しシャイな人が多いと感じます。
熱い思いを持っているのに、自分の意見やアイデアをあまり口にしない。だからこそ、もっと「やりたいこと」を言語化して、広く発信してみると良いのではないでしょうか。
もう一点感じるのは、アイデアの方向性がやや狭いことです。
「ゲームを作りたい」「LINE上のアプリを作りたい」といった、自分のスマホの中だけで完結してしまうテーマが多いのは少しもったいない。
私は日野市で子どもと犬と暮らしていますが、そうした生活の中で、学生時代とは違う景色や課題の視点が見えてきました。
もし“明星大学らしいアイデア”を出すなら、キャンパスの外にある、普段行かない場所に足を運んでみることをおすすめします。
その一歩が、ありきたりな発想から抜け出すきっかけになるはずです。」
萩原先生:
「自分らしさ、自分の特徴の活かし方についてアドバイスがあれば教えてください。」
平藤氏:
「2社目に起業した会社が今年で10周年になるのですが、1社目のウェブ制作会社の頃に比べると、今はプロフェッショナルが増えているなとこの10年くらいで感じています。僕らの時代は一生懸命雑誌を読んで、時間をかけて身につけていきましたが、今はYouTubeでデザインやツールの使い方も短時間でいろんなことを学ぶことができます。
最初の起業は制作でしたが、今はプロフェッショナルな個人が増えているから、2社目は各種プロフェッショナル人材と共に制作をする、プロジェクトマネージメントに特化した会社を起業しました。クライアント企業と一緒に考えながらつくる、共創型Web制作支援(Stand By YouTM)というサービスを展開しています。」
萩原先生:
「最終的にできたもの、ビジュアルは認知できるけど、そこに至るプロセスは想像できないですよね。ここにこそ、平藤さんの会社らしさがある。見せられない、見せようがないというのはつらいと思います。
個人の「らしさ」はブランディングですよね。自分でそれを把握して、最初は制作でクリエイティブだったのに、きちんとビジネスを学んできているのがすごいですね。足りない部分を見つけて取りに行っているのがすごいと思います。」
山根氏:
「プロセスは確かに見えませんが、成果物を通して「この人はこう考えるのか」「こんな性格なのかも」といった雰囲気は自然と伝わってくるものです。
少なくとも、自分なら作らないと感じるものに出会えたなら――それこそが、その人の”らしさ”なのだと思います。」
起業家に問う「自分らしい起業の育て方」

イベントの締めくくりは、伊藤先生やイベント参加者からパネリストへの質疑応答。コール&レスポンスにより、新たなクロッシングが生まれました。ここでは、質疑応答の一部を紹介します。
伊藤先生:
「好きなものを突き詰めていったらビジネスになったのが平藤さん。山根さんも自分が信じているものを突き詰めてビジネスにしている。このあたりはお2人の共通点ですね。その先のプロセス、物事へのアプローチの仕方にそれぞれの違いがあるように思います。
まず、平藤さんにお聞きしたいのが、ラボラトリー戦略について。ビジネスを続けることで競合が現れる。生き残るにはどうしたらいいのか、そのあたりをお聞かせください。」
平藤氏:
「ラボラトリー戦略は1社目に起業した以前の会社で試みたことですね。具体的にというと、今までやっていた仕事をやらないということに尽きる。毒を以て毒を制すみたいなもので、チャンスだけはない。チャンスにはリスクがある。経営としては投資が必要になりますが、チャンスとリスクの関係は表裏だと考えています。」
伊藤先生:
「新しい試みには痛みを伴うもの。一瞬利益が下がったり損が出たりするけれど、その先を見据えて大きなチャンスを掴んでいくということですね。ありがとうございます。
山根さんには、いかに社内の意志決定権を持つ人を説得してきたのか?というところをお聞きしたいです。」

山根氏:
「社内稟議の通し方ですね。
社内には、それぞれ個性の強い“厄介な人”がたくさんいます(笑)。
数字が好きな人、AIをとにかくやりたい人、求人を伸ばしたい人──みんな方向性が違う。
だからこそ、まずは相手の特性を見極めることが大切です。
そのうえで、自分の実現したいことを「誰に」「どの順番で」持っていくか。
ここが最初の戦略になります。
もうひとつのポイントは、PoC(Proof of Concept)をできるだけ安く始めること。
「これだけ低コストで、すぐに動かせて、3年後には数十億の利益が見込めます」
──このくらいシンプルで具体的な説得力を持たせるのが理想です。
初期投資が小さく、短期で利益の筋が見えていれば、基本的に“NO”という人はいません。
銀行の融資判断も、実は同じ理屈なんです。」
経営学部の学生:
「自分らしさや好きなこと、やりたいことが定まっていない、リソースもないのですが、起業したいと思っています。まず何を始めたらいいのかを知りたいので教えてください。」

平藤氏:
「なぜ起業したいのか?まずはその問いの答えを考えてみると良いかもしれません。起業はただお金を稼ぐだけではない。お金を稼ぐだけなら起業じゃなくてもできます。僕にとっては、社会に良い影響を及ぼしたり、仲間やクライアントとWin Winの状況でお金を稼げるのが一番良いなと思っています。
以前手掛けた女性クリニックの不妊治療のプロモーションのような仕事が理想です。他人に相談しにくい風潮のある不妊治療の理解を社会に促すような仕事でした。社会が自分が思う良い方向に変わるようなことができて、お金稼ぎができたらいいなと思っています。そういったことをビジネスと一緒に考えてみてはいかがでしょうか?」
山根氏:
「起業はあくまで手段の一つであり、目的ではありません。
やりたいことに最短で近づける道が起業なら、もちろん挑戦すべきです。
しかし、そうでないなら他の手段を選んでもいい。
「自分にとっての最適解は何か」を一度立ち止まって考えることが大切です。
それから、この手の悩みは人間よりAIに聞いてみるのもおすすめです。
AIは感情に流されず、膨大な情報と根拠から整理してくれる。
人間が“その時の気分”で言いがちなアドバイスを、ふわっとまとめて言語化してくれますからね(笑)。」
参考:24時間なんでも質問できる「山根GPTs」
https://chatgpt.com/g/g-67f95a232a1881919e961b6efa548668-shan-gen-tomentarinku
最後に

今回の「CROSSING DAY 2025 SUMMER」も、見どころの多い盛りだくさんの内容となりました。パネリストのお2人からも、リアルで有益なお話を聞かせていただき、起業を志す参加者にとって得るものが多い時間となったのではないでしょうか。「Meisei Crossing Base」のこれからの活動にもご期待ください!